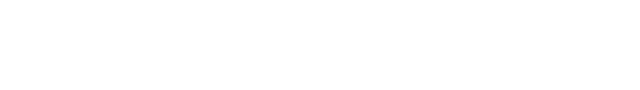小児喘息
小児喘息とは
小児喘息とは、子どもの気道(空気の通り道)に慢性的な炎症が起きて、繰り返し咳やゼーゼーする息苦しさ(喘鳴)を起こす病気です。日本では小児喘息患者は3歳までに80%が発症しており、男の子に多いといわれています。小児喘息のり患率や入院数、そしてなくなるかたは減ってきております。(喘息により不幸にもなくなられる15歳以下の人数は2020年以降1~3人/年です。 厚生労働省 人口動態統計より)
子どもの喘息は成長とともに良くなることもありますが、きちんと治療しないと約50%が成人へ移行したり、成人になってから喘息が再発することがわかっています。夜間や朝方に咳で眠れない、運動中に苦しくなる、救急受診を繰り返すなどの影響が生活の質(QOL)を下げてしまうため、早めの診断と治療がとても大切です。
小児喘息の原因と症状
喘息の原因は「気道のアレルギー性炎症」と「気道の過敏性」にあります。空気の中に含まれるホコリやダニ、花粉、ウイルス、タバコの煙などがきっかけとなって、気道に「炎症」が起き、通常は反応しない刺激に「過敏」に反応し、気道が狭くなり、咳や呼吸困難を引き起こします。アトピー性皮膚炎や食物アレルギーを持っていたり、ご家族が喘息やアレルギー体質だったときには、喘息の可能性が高くなります。
主な症状
- 夜間や明け方に続く咳
- 息を吐くときのゼーゼー・ヒューヒュー音(ぜんめい)
- 息苦しさ、呼吸が速くなる
- 運動すると苦しくなる
- 風邪をひいたあとに長引く咳
風邪と見分けがつきにくいことがありますが、咳や喘鳴(ぜんめい)を繰り返している場合は、喘息の可能性を考えます。
小児喘息の検査と診断
乳幼児期(5歳以下)と学童期(6歳以上)では診断の方法が異なります。
- 乳幼児期の場合にはウイルス感染にかかることも多く、また呼吸機能検査を行う事が難しいため、症状(ぜーぜー、ヒューヒューを繰り返す。アトピー素因や家族歴がある。)や、気管支拡張薬(β刺激薬)、吸入ステロイド(ICS)、ロイコトリエン拮抗薬への治療への反応をみて、診断することが多いです。
- 学童期以降では、検査を理解して行えることが多いため、以下の検査を組み合わせて診断していきます。
肺機能検査
装置に対し息を吸ったり吐いたりして、肺活量や、一秒間に吐ける空気の量を測定し、肺の機能を調べます。
呼気NO(エヌオー)検査
装置に対し8~10秒ほど、一定の強さで息を吐き、その中の一酸化窒素濃度(NO)を調べ、気管支の炎症の強さを調べます。
気道抵抗検査(モストグラフ)
装置に対し5~10回程度、普通の呼吸をすることによって、気道の狭さを見る検査です。結果は目で見てわかりやすい図で出てきます。非常に簡単にできる検査です。
特異的IgE抗体検査
アレルギーを持っているかを調べる検査です。大人と同じように採血していろいろなアレルゲンを調べることもできますが、小児の場合、ごく少量の血液(0.1ml)を指先や耳から痛みの少ない針で採取し、20分ほどで結果がわかるイムノキャップラピッドという方法を提案しております(大人にもできます)。この検査で分かるアレルゲンはスギ、シラカバ、ブタクサ、カモガヤ、ヨモギ、イヌ、ネコ、ヤケヒョウダニといった、気道アレルギーを起こしやすい代表的な8項目です。
小児喘息の治療(2023年ガイドライン準拠)
治療の目標は、症状のない生活を送れるようにすることと、肺機能を正常な状態にすることです。環境整備(アレルゲンを排除する)、運動療法(呼吸筋をきたえる、肺活量をきたえる)、薬物療法(気道の炎症をしずめる、気管支をひろげる)の三本柱で治療します。「小児気管支喘息治療ガイドライン2023」では、年齢と重症度に応じてどのような治療ステップを選択するかが決められております。またと、安定期の長期管理の治療と発作時の治療は異なってきます。代表的な薬物療法を記載します。
安定期の治療
以下の治療薬を重症度によって組み合わせて使用します。5歳以下と6歳以上で薬剤の使い方が変わってきます。
吸入ステロイド
喘息治療薬の基本的、かつ最も大切な治療薬です。気道の炎症を抑えるお薬です。様々な形や、薬剤を粉で吸うタイプ、ガスで吸うタイプ等があります。吸入するのが難しい方には、吸入補助具(スペーサー)を使用して使うことができます。
長時間作用型β2刺激薬
長時間にわたり気管をひろげ、息をするのを楽にするお薬です。吸入薬、内服薬、貼付薬などのタイプがあります。患者さんの年齢等を考え、どんなタイプのくすりにするか決めていきます。
吸入ステロイド+吸入長時間作用型β2刺激薬
ステロイドと気管支拡張薬が一緒になっている吸入薬です。一つの吸入薬で2つの薬剤を吸えるため、使いやすく、継続しやすいメリットがあります。粉のタイプとガスのタイプがあります。
内服ロイコトリエン受容体拮抗薬
気道を収縮させるロイコトリエンという化学物質をブロックして気道をひろげる薬です。炎症をしずめる効果もあり、比較的短時間で効果が表れやすく、運動前に内服すると「運動誘発性喘息」を予防するなどの効果もあります。
内服テオフィリン
気管支をひろげる効果があります。使いやすさの面で近年はやや出番の少なくなっているお薬です。
ダニアレルゲン特異的免疫療法
当院では舌下免疫療法が施行可能です。喘息のみへの保険適応はありませんが、ダニのアレルギー性鼻炎を合併した呼吸機能が安定している6歳以上のすべての喘息の方に有効な治療です。鼻炎(上気道)のコントロールを行う事が喘息(下気道)の改善をもたらし、吸入ステロイドの減量や、呼吸機能の改善をもたらし、下気道感染のエピソードを減少させ、発作を抑制することがわかってきました。
生物学的製剤
6歳以上の重症持続型の喘息に適応があります。ゾレア、ヌーカラ、デュピクセント、テゼスパイア、ファセンラといった皮下注射のお薬です。それぞれ効果が出やすい喘息のパターンなどによって使い分けます。注射の頻度も薬剤によって異なります。ファセンラ以外は自宅で注射をすることが可能です。
※治療は医師の診断のもと、お子さんの重症度に合った方法で安全に進めていきます。状態が良くなればステップダウン(薬を減らす)を行っていきます。過剰な治療や過少の治療を避けるように行います。
外来での発作時の治療
短時間作用型吸入β2刺激薬
通常5分以内に効果がでます。気管支をひろげ、息をしやすくします。状況によって、20分ごとに3回程度繰り返すことがあります。
全身投与ステロイド
果がでるまでに数時間かかりますが、気道の炎症をとり、発作が長引かないようにします。
アミノフィリン点滴
気管支をひろげます。ただしけいれんの副作用があるため、2歳未満、けいれんの既往、副作用の既往がある場合には投与を行いません。
酸素投与
酸素飽和度が低いとき(SpO2 94%以下)やチアノーゼが出ているときには投与を行います。
アドレナリン(ボスミン)皮下注射/筋肉注射
重症なときには投与します。
*酸素を必要とする時や、アドレナリンの注射を必要とするときには入院を考慮します。
よくある質問(Q&A)
Q1. 喘息って治るんですか?
A. 成長とともに症状が落ち着く子も多いですが、適切な治療をしないと約50%の方が症状を引きずったり、大人で再発します。そのうちよくなるだろうと様子をみるだけでなく、症状が長引いたり、繰り返すようなら治療したほうがいいかどうかを一度ご相談ください。
Q2. ステロイドの副作用が心配。治療をやめることができるの?
A. 確かに小児期に長期間ステロイドを使用すると、使わなかった子と比較して身長が2㎝低くなる可能性が指摘されております。ただ、だからといって喘息の治療をしなければ、生涯にわたって喘息に苦しめられたり、若くして肺気腫(COPD)になってしまうリスクが高まり、何より日常生活の質が落ちてしまいます。一緒に相談しながらお子さんにとって最適な対応を選択していきましょう。
Q3. 家で気をつけることは?
A. ダニやホコリを減らすために掃除・換気をこまめに行いましょう。室内飼育のペットがアレルゲンの場合、適切な距離感をもつことが大切です。たばこの煙や香りの強い洗剤・芳香剤も避けましょう。受動喫煙は喘息発症の最大のリスクの一つです。同居の方で喫煙されている方はぜひともタバコをやめてください。
Q4. すぐに病院に行くタイミングは?
A. 唇や爪の色が白っぽい、横になって眠れない、会話ができない、息を吸うと胸がペコペコへこむ、ボーとしている、脈がとてもはやいなどのときはすぐに病院、医療機関へ受診してください。場合により救急車の要請も検討してください。
院長より皆様へ
小児喘息は診断がむずかしく、長くつきあう病気ですが、正しい知識とケアで大きく改善が期待できます。お子さんは自分で喘息かもしれないとは考えつきません。ぜーぜーが治らない、ずっと咳をしている、もしかして自分の子供は喘息かもしれないと親御さんがおもったなら、ぜひ一度ご相談ください。