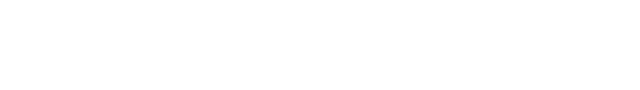小児科診療
はじめに
私と副院長は小児科専門医ではありませんが、内科、呼吸器、アレルギー疾患を専門とする立場から、お子さんの役にも立ちたいと考えております。こどもによくみられる発熱、インフルエンザや感染症、咳、腹痛、下痢、嘔吐などのコモンディジーズ(一般的な症状)に初期対応いたします。また小児喘息などの呼吸器疾患、花粉症やアレルギー性鼻炎などには専門的な立場からも診療にあたります。ただし子供の食物アレルギーの確定診断には食物経口負荷試験が必要になります。その際には基幹病院への紹介をさせていただきます。
小児ワクチンの摂取は適宜行っております。
1. よくある症状への対応:発熱・咳・鼻水・下痢・便秘など
お子さんによく見られる風邪のような症状、たとえば「熱が出た」「咳が続く」「下痢や嘔吐がある」などは、多くがウイルスなどによる一時的な体の反応が考えられます。これらは「コモンディジーズ」と呼ばれ、日常的によく見られる病気です。当院では、いわゆる風邪症状に対しては、発熱外来を設けており、一般の診察室とは分けて、発熱外来にて診察を行います。待合室も専用の待合室を設けますが、車で待機することもできます。(発熱外来の運用は状況によって変わることがあります)感染症の迅速検査もそれぞれ行っております。重症と考えられた場合には入院も検討し、最適な医療機関に紹介いたします。丁寧にお話を聞き、必要な診察や検査を行い、早めに安心できるような対応を心がけています。
2. 小児喘息について
小児喘息は、気管支(空気の通り道)が過敏になり、咳やぜーぜーとした音(喘鳴)が出る病気です。3歳までに80%が発症し、男児が多いです。多くの場合、夜間や朝方に症状が強く出ます。成長とともに治まることもありますが、きちんとした治療を続けることがとても大切です。当院では、定期的な吸入薬の使用や症状の記録をもとに、お子さんに合った治療方針を考えていきます。また、アレルギーとの関係も深いため、アレルギー検査も適宜提案していきます。喘息の治療の基本は環境整備(原因を見つけて、遠ざける)です。吸入薬の基本はステロイドですが、ステロイドの副作用や将来的なリスクを心配されるのは親として当然だと思います。全員が全員吸入ステロイドを吸わなければならないわけではありません。例えば年に数回、季節の変わり目にのみ症状がでる場合には吸入ステロイドなどの長期管理薬は必須ではありません。小児気管支喘息治療・管理ガイドラインにのっとり、ひとり一人の重症度によって適切な治療をそれぞれ提案します。ご不安なことがあればぜひ一度ご相談ください。
小児喘息に関して詳細はこちら
3. 花粉症、アレルギー性鼻炎について
今や日本人の約50%が何らかのアレルギー性鼻炎を持っています。アレルギー性鼻炎は花粉、ダニ、ペット(ネコが多い)のふけなどの抗原(アレルゲン)に対しての過剰な体の反応です。まずアレルゲンを調べ、避けることが可能なのかどうかを検討します。そのうえで症状に合わせたお薬の提案を行います。日本ではスギとダニに対して5歳以上に舌下免疫療法という根本治療が保険適応されており、当院でも対応しております。治療効果はすぐには出づらいため、受験を考えているお子さんやつねに鼻水がでて、生活の質が下がっているお子さんはぜひ相談してください。
4. 食物アレルギーとその診断
「卵を食べたらじんましんが出た」「ピーナッツで息が苦しくなった」など、食べ物によるアレルギー反応は、子どもにとって命に関わることもあります。ただし、アレルゲンの採血検査だけで本当にアレルギーかどうかはわからないこともあります。確定診断には「食物経口負荷試験」が必要ですが、これは安全のため入院設備のある病院で行った方がいいと考えられます。当院では、疑わしいケースを丁寧に見極め、必要に応じて連携病院へ紹介いたします。
*一度の採血で30~40種類の多くのアレルゲンを調べるセットの検査がありますが、特に食物アレルギーに対しては、判断が難しい検査となっております。食べることができるのに検査で陽性になってしまったらどうしたらいいのか判断に迷われる方も出てきています。食物アレルギー検査の原則は、「食べて症状がでたものに対して検査を行う」ことです。特にお子さんは栄養の面からも様々な食物を摂取することが必要です。採血で陽性になっても食べて症状がでないなら、食べて大丈夫が原則です。
5. アトピー性皮膚炎の治療
かゆみをともなう湿疹が長く続くアトピー性皮膚炎は、子どもにもよくある皮膚の病気です。肌のバリアが弱く、外からの刺激に反応して炎症を起こします。当院では、保湿剤やステロイド軟膏など、肌の状態に合わせた塗り薬の使い方をしっかり説明し、無理のない治療をすすめています。症状が強かったり、なかなか改善しない場合には、皮膚科の専門医と連携していきます。
6. 小児のワクチン接種
ワクチンは、こどもを重い病気から守る大切な手段です。当院では定期予防接種(五種混合、MR、Hibなど)や任意接種(おたふくかぜ、インフルエンザなど)も対応しています。接種スケジュールや注意点については、個別に説明しながら、安全に接種できるようサポートします。母子手帳をお持ちいただければ、接種状況の確認もできます。
別途ワクチンのページもご参照ください。ワクチン接種は原則予約制で対応いたします。
7. 当院でお子さんにも行う事ができる主な検査
検査は一人一人の症状や必要性によって、どんな検査を行うかをお伝えしたうえでと相談しながらおこなっていきます。
迅速感染症検査
インフルエンザ、溶連菌、コロナウイルス、アデノウイルス等各種の感染症検査が可能です。
血液検査、尿検査
すぐに結果が出るものとしては、血算(白血球3分類、赤血球、血小板)、CRP(感染、炎症の強さを見る検査)、尿検査が可能です。また外注の検査会社でほとんどの血液検査を行う事が可能です。
アレルギー検査
院内ですぐに(20分程度)結果がでる検査として、イムノキャップアレルゲン8を導入しております。花粉症やアレルギー性鼻炎に対しての検査で、花粉系(スギ・ブタクサ・カモガヤ・ヨモギ・シラカンバ)とハウスダスト系(イヌ、ネコ、ヤケヒョウダニ)の8種類に対しての検査です。この検査は血液の量が非常に少なくて(0.1ml)もできる検査で、指先やかかとからちくっと針を刺して血液を採取し安全にできる検査です。注射や採血が苦手なお子さんでもできる検査です。(イムノキャップアレルゲン8の図をはりつけ)
他のアレルゲンに関しては、採血を行い外注検査にて調べます。外注検査ではさまざまな抗原(アレルゲン)の血液検査が可能です。
プリックテスト
即時型アレルギー検査として有用です。抗原(アレルゲン)を皮膚にたらし、痛みを感じづらい針で皮膚を圧迫刺激し、15分後に膨らみの大きさで陽性か陰性か判定します。ダニやスギなどの花粉系から小麦粉、牛乳、卵黄、卵白などの食物系に対しての診断液があります。また診断液を用いずに、アレルギーを起こしている可能性のある食物を持参していただき、その食物を針で刺し、その針で皮膚を圧迫刺激する方法で判断することも可能です。事前の準備が必要になりますので、まずは外来で相談し、検査の予定を組んでいきます。
呼吸機能検査
肺活量の測定や、喘息など空気の通り道に病気があるかどうかの診断で行います。ただ行うのにコツがいる検査なので、ある程度高学年でないと難しい可能性があります。この検査ができない場合には他の呼吸機能検査を行い診断していきます。
気道抵抗試験
喘息の診断に非常に有用な検査です。マウスピースをくわえて機械にむかって普通に5~10回呼吸をするだけで、気管支喘息の可能性を判断できます。喘息の治療効果を見ていく上でも有用な検査です。指示に従うことができれば、3歳ぐらいからでもできます。
呼気一酸化窒素濃度検査(FeNO)
マウスピースを加え、10秒程度同じ力で機械に息を吹き続けます。少しコツがいりますが、喘息の診断や治療がうまくいっているかの判断に非常に有用な検査です。
レントゲン検査(一般撮影)
小児の場合、主に肺炎や気胸(肺に穴が開き、肺がしぼんでしまう病気)の有無を調べたり、腹痛などのときに行う検査です。何度も撮影しなければ被ばくはほとんど心配しなくて大丈夫ですが、必要なときのみ行います。
心電図検査
不整脈などを測定する検査です。
エコー検査
当院のエコーはポータブルエコーです。どこにでも持ち運ぶことができ、その場でぱっとあててみるのに優れています。小児に使う場面としては、主に腹痛などで、便秘や腸重積があるかどうかのスクリーニングで使用します。
8. 必要に応じた専門医・病院への紹介
当院でできることには限りがあります。症状が重かったり、より詳しい検査や治療が必要と判断された場合には、地域の基幹病院や専門医療機関へ速やかにご紹介いたします。患者さんとご家族が安心して医療を受けられるよう、責任をもってつなぎます。
保護者の皆さまへ
こどもは自分の体調をうまく言葉にできないことがあります。だからこそ、おやごさんの「ちょっといつもと違うかも?」という感覚を大切にしなければなりません。私は小児科専門医ではありませんが、お子さんとご家族の気持ちに寄り添いながら、一人ひとりに合った丁寧な医療を心がけていきます。