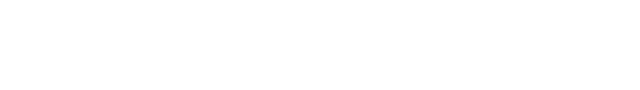気管支喘息
喘息
喘息は、子供から大人までを問わず多くの方に起こる呼吸器の病態です。適切な管理と治療で日常生活を安心して過ごすことを目指して治療し、臨床的寛解を目指します(症状のない状態)。私たちのクリニックでは、喘息の診断から日々のケアまで、一人ひとりに合わせたサポートを行っています。慢性的な咳や呼吸の苦しさでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
喘息(ぜんそく)とはどのような病気か
喘息(ぜんそく)は、空気の通り道である「気管支」に慢性的な炎症が起こり、咳や息苦しさ、ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音などの症状が繰り返し現れる病気です。アレルギー反応や感染症、寒暖差、ストレスなど、さまざまな刺激によって症状が悪化するのが特徴です。喘息の多くは2~3歳に発症します。小学生の有症率は最近は減少傾向ですが、大人では増加傾向にあるという報告があります。
喘息の症状について
気管支喘息の代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 繰り返す発作性の咳(特に夜間や早朝)
- 呼吸をするとゼーゼー、ヒューヒューと音がする
- 胸がしめつけられるように苦しい
- 息を吐きにくい、深く吸えない感じがする
- 咳がなかなか治まらない。特定の環境や季節で苦しくなる。
これらの症状は、天候の変化やダニ、ほこり、花粉、タバコの煙、ストレスなどで悪化しやすい傾向があります。
ひどい発作が起こると、呼吸がしづらくなり、会話や食事も難しくなることがあります。命にかかわる重症発作に至ることもあるため、軽く見ず、適切な診断と治療が大切です。長期にわたって放置すると、気管支がもとに戻らない状況になり、薬剤の治療効果が得ずらい状況になります(リモデリング)。
喘息の原因について
喘息症状の主な原因は、気道の「過敏性」が高くなることです。つまり、健康な人なら反応しない程度の刺激にも気道が過剰に反応し、炎症が起きて気管支が狭くなってしまうのです。
喘息の発症には「遺伝因子」と「環境因子」が関係しています。統計的には両親のいずれかが喘息だと子供も喘息になる割合が高くなることがわかっていますが、喘息を診断できる遺伝子はいまだにわかっていません。
環境因子に関してはアレルゲンの多い環境や、RSウイルス、ライノウイルスなどの呼吸器感染症が喘息の発症に関与していると報告されています。ほかに発症にかかわる因子で明らかになっているのは(受動)喫煙です。親の喫煙は生涯にわたって子供の呼吸器に対し大きな影響を与えることが分かっています。
気道の「過敏性」を起こす因子の例を挙げます。
| 因子の種類 | 内容 |
|---|---|
| アレルゲン(アレルギー物質) | ダニ、ハウスダスト、花粉、ペットのふけなど |
| 感染 | 風邪、インフルエンザなどのウイルス感染 |
| 刺激物質 | タバコの煙、排気ガス、香水、洗剤など |
| 天候の変化 | 寒暖差や気圧の変動 |
| 運動 | 激しい運動後に症状が出ることも |
| 精神的な要因 | ストレス、不安、緊張など |
| 薬の種類 | 役割 |
|---|---|
| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を抑える(基本となる治療) |
| 長時間作用型気管支拡張薬 | 気道を広げて呼吸を楽にする |
| 発作時の吸入薬 | 発作時に即効性を発揮して息苦しさを改善 |
| 抗アレルギー薬 | アレルギー反応を抑える |
喘息の種類(タイプ分類)
喘息は原因によりタイプ分類されます。2型炎症細胞性喘息/非2型炎症細胞性喘息(好中球性など)に分かれます。さらに2型炎症細胞性喘息はアトピー性喘息と好酸球性喘息、またはその両者のアトピー性好酸球性喘息のタイプに分かれます。喘息のタイプによって、治療方法が変わってくることがあるため、当院ではできるだけ喘息のタイプまで調べてそれぞれのタイプに最適な治療方法と提案します。
症状による喘息の分類
咳喘息
咳だけが症状で、ゼーゼー(喘鳴)や息苦しさが目立たないタイプです。アトピー咳嗽との鑑別が問題になります。風邪のあとに長引く咳の原因となることが多く、放置すると喘鳴を伴う喘息に移行することもあります。治療は気管支拡張薬を中心に喘息の治療を行います。
運動誘発性喘息(アスリート喘息)
運動のあとや寒い時期のランニングなどで、咳や息切れが出るタイプです。スポーツを続ける上でも、適切な予防と継続治療が大切です。
アスピリン喘息(NSAIDs過敏喘息)
解熱鎮痛薬であるNSAIDsやアスピリン(バファリン)で発作が出現することがある。小児ではまれであり、30-40代の成人喘息の5-10%に出現し、女性にやや多い。半分は重症喘息であるが家族内発症はほとんどなく、遺伝的背景は強くない。鼻茸、慢性副鼻腔炎、好酸球性中耳炎、嗅覚障害を合併していることが多く、着色料(食用4号)、練り歯磨き粉、ミント、アルコールなどで悪化することがあります。
ACO(喘息とCOPDの合併)
喘息とCOPDが合併する病態です。治療は喘息の治療とCOPDの治療を行いますが、喘息よのみよりも治療が難渋することが多いです。
職業性喘息
特定の労働環境で特定の職業性物質に暴露されることで起こる喘息と定義されます。
成人喘息のうち頻度は5-20%です。作業従事により症状誘発され、離れれば軽快します。
高分子量物質(植物性物質、動物性物質など)、や低分子量物質(化学物質、薬品)に感作されて発症する感作物質誘発職業性喘息と、刺激物質(塩素、酢酸、煙など)によって誘発される刺激物質誘発職業性喘息の二つに大きく分類されます。近年では洗剤の暴露による喘息が増加している。治療は原因の回避と一般的な喘息の治療です。
喘息の検査
血液検査
血液検査では総IgE(アレルギー体質の人で高くなる)、好酸球(アレルギー性炎症があると高くなる)、アレルゲン特異的IgE検査(ダニ、花粉、ペット、食物等)、を調べ、アレルギー性喘息か、好酸球性喘息か、アレルギーが関与しない喘息か検討し適切な治療を選択します。
呼吸機能検査
呼吸機能検査ではフローボリューム曲線(思いっきり息を吐いた時の空気の流れを見える可した検査)や、一秒率(1秒間の間にどれくらいの息を吐くことができるのかの割あい)を調べ、喘息やCOPDの診断や、治療効果を判定していきます。
呼気一酸化窒素濃度(呼気NO)
気道の炎症の程度を数値で測定します。NOが高い時には一般的に喘息による気道の炎症の程度が悪い状態を示します。(余談ですが、私が大学院生時の研究テーマの一つとして実験しておりました。)
気道抵抗検査(モストグラフ)
気道の狭さを見る検査です。呼吸機能検査や呼気NO検査は検査にコツがいりますが、モストグラフはマウスピースを加え、普通に呼吸をするだけで気道が狭い状況かどうか分かり、また喘息とCOPDの鑑別判断にも使用できます。
個々人で施行可能な検査を組み合わせて、咳の原因や喘息やCOPDの診断、そして治療効果を判断していきます。
気管支喘息の治療について
当院では、喘息治療ガイドラインに基づき、患者さん一人ひとりの症状や重症度、生活スタイルに合わせた適切な喘息の治療を行っています。
薬による治療
喘息治療では、以下のような吸入薬や飲み薬などを使用し治療します。以下に代表的な薬剤を記します。
①吸入ステロイド
気管支の炎症を抑えます。喘息は気道に炎症が生じている病態です。そのため吸入ステロイドを使用し気道の炎症を抑える治療が、喘息の一番の主役になります。さまざまな強さの吸入ステロイドがあり、吸入するためのデバイス(装置)もたくさんの種類があります。患者さんの年齢や吸入する力、一日の吸入回数、アルコール成分への過敏があるかなどを考え、一人ひとりに最適な薬剤を選択します。気管支拡張薬と一緒になった合剤もあります。ほとんどの場合吸入したステロイドは肺内で代謝されますが、ごく微量血液中に移行することがあります。そのためお子さんが長期間使用した場合に身長への影響を心配されることがあると思いますが、適切な薬剤を使用せずに喘息発作を繰り返すことのほうが、成長への影響が懸念されます。治療の中止は決して自分で判断せず、医師と相談しながら決めていきましょう。
②長時間作用性β2刺激薬(吸入、貼りぐすり)・短時間作用性β2刺激薬(吸入)
気道炎症により気道過敏が亢進(様々な刺激に反応してしまう状況)すると、気道が狭くなり、呼吸がしづらい状況になってしまいます。β2刺激薬等の気管支拡張薬を使用することによって、気道を広げ、呼吸をするのを楽にします。長時間作用するタイプには吸入薬や、貼り薬などがあります。吸入ステロイドと同様に、年齢や吸入する力、併存症の有無により使い分けます。喘息の維持治療としては吸入ステロイドと長時間作用性β2刺激薬が一つの吸入装置に入った合剤を使用することがあります。苦しくなった時にレスキューとして使用する短時間作用性β2刺激薬は気管支拡張効果が短時間(5分以内)で出現しますが、気管支拡張効果が短時間しか続かない(15分程度)ため、あくまで発作時に使用します。内服薬もあります。発作が頻回にあるのに、短時間作用性β2刺激薬のみで治療することは副作用や治療の観点からもお勧めできません。一度治療を見直してみましょう。
③長時間作用性抗コリン薬(吸入)
β2刺激薬とは違う作用で気管支収縮を防ぐことで気管支を拡張させます。比較的重症の喘息の方に使用します。大人の場合、緑内障や前立腺肥大症があると副作用が出やすいため、安全に使えるかどうか診察しながら必要な場合に吸入ステロイドや吸入β2刺激薬と併用するか検討します。吸入ステロイド/吸入長時間作用性β2刺激薬/吸入長時間作用性抗コリン薬が一つになった吸入薬もあり、比較的重症な喘息の方に使用します。
④ロイコトリエン受容体拮抗薬(内服)
気管支を収縮するロイコトリエンの受容体に作用し、気管支が収縮するのを防ぎます。ロイコトリエンは鼻粘膜の炎症や鼻づまりを引き起こすため、ロイコトリエン受容体拮抗薬はアレルギー性鼻炎の治療にも使用されます。
⑤テオフィリン製剤
気管支の拡張作用や、呼吸中枢を刺激することで喘息の咳や息苦しさを改善します。ただし薬剤が効きすぎると副作用をきたしやすい薬であるため、時々採血を行い、薬剤が効きすぎないように内服量をコントロールする必要があります。少し使いづらい薬ですが、うまく使用すれば今でも有効な治療薬です。
⑤生物学的製剤
吸入ステロイド、長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、テオフィリン製剤等を使用しても喘息症状のコントロールが難しい重症喘息の場合に選択肢となります。皮下注射の薬剤で、初回はクリニックで施行し、2回目以降は自宅で自己注射することが可能です。現在日本では5種類の生物製剤を喘息に対して使用可能です。それぞれの生物製剤は投与期間や最もよく効く喘息パターンが異なります。非常に有効な治療ですがデメリットとしては定期的な皮下注射を行わなければならいことと、高価であることです。
上記の薬剤を、重症度に合わせ薬を正しく使用することで、発作の回数や重症化のリスクを減らし、臨床的寛解を目指します。
環境整備と生活指導
喘息を悪化させる要因を避けることも大切です。
- 部屋をこまめに掃除してダニ、ハウスダスト、ペットのふけを減らす
- ペットと同じ空間で寝ない
- 禁煙を心がける
- 感染症予防を行う
- また、定期的な通院で症状のコントロール状況を確認し、必要に応じて治療を見直していきます。
気管支喘息についてのよくある質問
Q. 喘息は治りますか?
A. 小児喘息は適切な時期に最適な治療を行えば完治(治療を必要としない状況)も可能と考えます。成人になってから発症した喘息は完全に「治る」というよりは、完全に症状をコントロールできる(臨床的寛解)を目指せる病気と考えた方が良いです。重症度や喘息のタイプごとに、適切な薬を使用することで、喘息を気にせずに日常生活を過ごせる状態を目指します。
Q. 発作が出ていないときは通院、治療はしなくてよいですか?
A. 発作が出ていない時でも、炎症が進行している場合があります。症状が安定していても、定期的な診察、治療が大切です。小児喘息は適切な治療を行えば50%が完治すると言われていますが、きちんと治継続療しないと50%は再発し、成人期へ移行するといわれています。
Q. クリニックではどんな検査や治療ができるのですか?
A. 当院は咳や喘息、アレルギーに関しては特に診療に力を入れております。喘息の検査機器も大きな病院に引けをとらないように揃えており(呼吸機能検査、呼気NO検査、気道抵抗検査、各種アレルゲン検査等)、患者さんの年齢、重症度、生活スタイルに合わせて適切な治療と環境整備のアドバイスを行っております。
院長より
喘息は大学での私のメイン研究テーマの一つで、学位論文も喘息の基礎研究で取得しました。私たちのクリニックでは、気管支喘息の診断・治療はもちろん、患者さんの生活に寄り添ったサポートを大切にしています。喘息は「正しく知って、うまくコントロール」ことがポイントです。
「咳が止まらない」「夜に苦しくて目が覚める」などの症状がある方は、どうかご自身だけで抱え込まず、私たちにお話しください。安心して笑顔で毎日を過ごせるよう、しっかりサポートいたします。