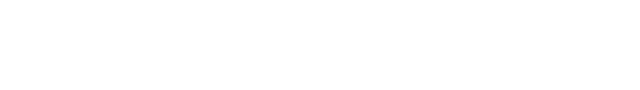小児食物アレルギー
私は小児科専門医ではありませんが、アレルギー疾患を横断的に診療する中で、成人食物アレルギーに関しても臨床経験と知見を持っております。成人と小児では臨床症状も異なり、対応の仕方も変わってきますが、小児食物アレルギー診療にもいかせるところはあると考えております。当院では問診から食物アレルギーの可能性を疑い、採血などで検査し、疑わしい場合には、適切な施設へ食物経口負荷試験等の確定診断目的に橋渡しを行います。お子様のお役に立てればと考え、以下に情報提供目的に記事を作成いたしました。ご参考になれば幸いです。
食物アレルギーとは?
食物アレルギーとは、特定の食べ物を食べた時に体の免疫が過剰に反応し、皮膚・呼吸器・消化器などに症状を起こす病気です。小児では特に0~1歳の乳児期に多く見られます。主な原因食品は卵、牛乳、小麦が中心ですが、最近は木の実や魚卵、甲殻類なども増えています。特にナッツ類は小麦より頻度が多くなってきており、注意が必要です。
アレルギー反応は多くが食後数分〜2時間以内に起こりますが、まれに遅れて出現することもあります。重い場合にはアナフィラキシーという命に関わる状態になることもあるため、正しい理解と対応が大切です。
小児の食物アレルギーの特徴と推移
乳児期に始まる食物アレルギーの多くは、成長とともに自然に治る(寛解する)ことが多いです。特に卵・牛乳・小麦アレルギーは6歳ごろまでに7~8割の子どもで改善がみられます。しかし、ナッツ類や魚介類によるアレルギーは寛解しにくく、長期にわたって注意が必要です。
また、乳児期のアトピー性皮膚炎や食物アレルギーやが、将来の喘息やアレルギー性鼻炎につながることがあり、これを「アレルギーマーチ」と呼びます。
口からではなく、皮膚から食物が入ることで(経皮感作:けいひかんさ)、食物アレルギーをおこしやすくなります。乳児湿疹やアトピー性皮膚炎がある場合には、まず徹底して皮膚の状況をよくすることが必要です。皮膚科や小児科の指導のもと、治療をおこなってください。ただし、皮膚の状態が改善しないからといって、離乳食開始時期を遅らせることは現時点では有効な手段ではないと考えられています。皮膚にトラブルがある場合は、様子をみすぎるのではなく、なるべく早く皮膚の状況を改善させるように医療機関を受診してください。
3.食物アレルギーの種類と症状
| 臨床型 | 発症年齢 | 頻度の高い食物 | 寛解のしやすさ | アナフィラキシー ショックの可能性 |
|---|---|---|---|---|
| 食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎 | 乳児期 | 鶏卵、牛乳、小麦 | 多くは寛解する | あり |
|
即時型症状(じんましん、アナフィラキシーなど) |
乳児期~成人期 | 鶏卵、牛乳、小麦、ピーナッツ、ナッツ類、魚卵、甲殻類など | 鶏卵・牛乳・小麦は寛解しやすい、その他はしにくい | 高い可能性あり |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA) | 学童期~成人期 | 小麦、エビ、果物など | 寛解しにくい | 非常に高い可能性 |
| 口腔アレルギー症候群(OAS) | 幼児期~成人期 | 果物・野菜・大豆など | 軽症だが継続しやすい | 低い(基本的に局所) |
参考:アレルギーの手引き2025 表8-1より 再編集
検査と診断の流れ
| 検査方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 血液検査(特異的IgE) | 採血でアレルゲンに対する抗体の有無を調べる。 |
偽陽性(検査では陽性だが実際には症状がでない)に注意が必要。卵白・牛乳・小麦・ピーナッツはIgE抗体価で症状が誘発される可能性を予測することができる。 |
| 皮膚プリックテスト | 採血しなくてよい。アレルゲンを皮膚に少量つけ、針で刺激し反応を見る。 | 6か月までの乳児で特に感度が高い。抗原を選ばず検査できるが、まれだがアナフィラキシーのリスクがある。 |
| 食物経口負荷試験 | 実際にごく少量ずつ食べて症状の再現性を見る。 | 確定診断方法であり、小児では施行を考えるべき検査。当院では行っておりません。 |
※診断には、詳細な問診が重要です。小児の場合、成長に必須な栄養が取れなくなってしまう可能性があるため、採血や皮膚テストの検査結果のみでご自身の判断で食物除去を決定することはおすすめしません。確定診断には食物経口負荷試験を検討しましょう。ただし当院では食物経口負荷試験は行っておりません。症状、問診、血液検査等から食物アレルギーが疑われ、検査の適応があると判断した場合には食物経口負荷試験が可能な病院に紹介のうえ、実施を検討していただきます。
食物アレルギーの治療と管理
一般的に食物アレルギー(卵、牛乳、小麦、大豆)は年齢とともに改善し、日常生活で摂取可能な量を食べても症状がでない状況になることが期待できることが多いです。その一方、甲殻類(エビ、カニ)、ナッツ類、魚卵、魚、軟体類(イカ、タコ、貝)、そばなどは耐性を獲得しづらいと報告されています。管理の基本は、「これまで食して症状が出た食べ物だけを、必要最小限除去すること」です。また現時点では・妊娠中や授乳中の母親の食物除去は不要である ・乳児湿疹やアトピー性皮膚炎に対しては積極的なスキンケアを行う方が食物アレルギーが少なくなる ・離乳食を遅らせることは食物アレルギー発症を予防せずむしろリスクになる ことがわかっています。
主な対応策
- 除去食:原因食物だけを必要最小限除去する。成長に関わるため、症状が出たことがない食物に対しての予防的な過剰な除去は避ける。
- 栄養指導:管理栄養士による代替食品の提案等。
- エピペン®の携帯:アナフィラキシーの既往がある方に処方。
- 食物経口負荷試験:食べられる量の確認や制限の解除の判断に活用。
- 経口免疫療法(OIT):一部の専門施設で研究的に行われる。医師の管理が必要。食べられる量を増やしていき、万が一誤食しても命に関わる状況を防ぐ。
このように、小児食物アレルギーの管理には専門的知識が必須で、専門施設での対応が望まれます。当クリニックでは食物アレルギーの治療や管理よりも、専門医療機関と患者さんをつなげる橋渡しの役割を担っていきます。
よくある質問(Q&A)
Q.アレルギーは一生続きますか?
多くの子どもは成長とともに改善します(牛乳:6歳までに85%が牛乳200mlの摂取が可能になる。小麦:6歳までに66%が日常生活量を摂取できるようになる。鶏卵:6歳までに66%が過熱全卵1/2個を摂取できるようになる)が、ナッツや魚介類は長く続くことがあります。
Q.除去する食品と量はどう決めるの?
医師の診断と負荷試験の結果に基づき、必要最小限で除去します。専門医療機関での判断が望ましいです。
Q.学校や保育園での対応は?
生活管理指導表を提出し、除去食やエピペン対応などを行います。
Q.採血検査で陽性でも食べてもいい?
実際に症状が出なければ食べても良いことが多いです。アレルギーが心配で、数十種類の結果が一度にでる多項目のアレルギー検査をした場合、陽性になった時の判断に非常に困ります。検査は疑わしい項目に対してのみ必要最低限行う事をお勧めします。
院長より
食物アレルギーは、お子さまにとっても、またご兄弟やおやごさんにとっても大きな心配の種となりますが、正しい診断と管理、治療を行えば、安心して毎日の生活を送ることができます。当院では、小児食物アレルギーの治療よりも、専門医療機関と患者さんをつなげる橋渡しの役割を担っていきます。食物アレルギーを疑った場合には、一度ご相談ください。