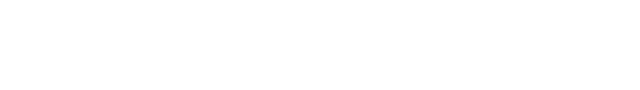睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
睡眠時無呼吸症候群(すいみんじむこきゅうしょうこうぐん)は、寝ている間に呼吸が何度も止まる(病態としては上気道の閉そくですが、便宜上呼吸が止まるとして説明します)病気です。英語では「Sleep Apnea Syndrome(SAS)」と呼ばれています。
呼吸が止まると、体が酸素不足になってしまい、睡眠の質が下がるだけでなく、命に関わる病気のリスクも高まることがあります。いびきが大きい、昼間に眠くなる、集中力が続かない、記憶力が低下しているなどの症状があれば、もしかしたらSASの可能性があります。
日本における有病率とリスク
日本では、中等症以上のSASは約500万人以上と推計されていますが、実際に治療を受けている人はその一部に過ぎません。特に中高年の男性に多く見られますが、女性や若年層、子どもにも起こることがあります。
放置するとどうなるの?
睡眠時無呼吸を放っておくと、以下のような合併症を引き起こす危険性があります。
- 高血圧
- 心筋梗塞、脳梗塞
- 不整脈
- 糖尿病の悪化
- 交通事故(居眠り運転など)
日常生活にも支障をきたし、命に関わる合併症のリスクとなる可能性があるため、早期の発見と継続治療がとても大切です。
睡眠時無呼吸の原因と症状
原因
睡眠時無呼吸には、主に次のような原因があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 閉塞型(OSA) | 上気道(のど)が寝ている間にふさがってしまう。主には舌根沈下が原因。SASの約9割以上を占める。 |
| 中枢型(CSA) | 脳からの呼吸指令が出なくなる。心不全などに伴って起きることも。 |
| 混合型 | 上記の両方が混じったタイプ。 |
閉塞型では、以下のような体質・生活習慣が影響します。
- 肥満
- 顎が小さい、首が短い
- 扁桃腺が大きい
- アルコールの飲みすぎ
主な症状
- いびきが大きい
- 息が止まる(家族に指摘される)
- 夜中に何度も目が覚める
- 起床時に頭が重い、だるい
- 日中の我慢できない眠気や集中力の低下
特に「大きないびき+日中の眠気」はSASのサインかもしれません。
睡眠時無呼吸の検査
まず以下の問診にこたえてみてください。
エプワース眠気尺度(ESS)問診票
あなたが以下の状況で眠ってしまう可能性について、普段の生活を思い浮かべながら点数をつけてください。
点数のつけ方
| 点数 | 意味 |
|---|---|
| 0 | まったく眠くならない |
| 1 | 時々眠くなる |
| 2 | よく眠くなる |
| 3 | ほとんど必ず眠くなる |
質問項目(各項目に上記に当てはまる0~3の点数を記入してください)
| 状況 | 点数(0〜3) |
|---|---|
| ① 座って読書をしているとき | |
| ② テレビを見ているとき | |
| ③ 人がたくさんいる場所(劇場や会議など)で静かに座っているとき | |
| ④ 乗客として車に1時間以上連続して乗っているとき | |
| ⑤ 午後に横になって休んでいるとき | |
| ⑥ 座って誰かと会話しているとき | |
| ⑦ 昼食後、静かに座っているとき(飲酒はしていない) | |
| ⑧ 自分で車を運転していて、渋滞などで数分間止まっているとき |
合計点(最大24点):_____点
評価の目安
- 0〜10点:正常範囲(ただし日常生活に支障がある場合は医師へ相談)
- 11〜14点:軽度の過眠傾向(要経過観察)
- 15点以上:中等度〜重度の過眠(医師の受診をおすすめします)
上記の問診で10点以上、または点数が低くても症状から睡眠時無呼吸が疑われる場合には検査を行っていきます。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の呼吸の状態を記録する検査で診断します。主に以下2つの検査方法があります。
検査方法の比較
| 検査名 | 内容 | 特徴 | 精度 | 実施場所 |
|---|---|---|---|---|
| 簡易アプノモニター検査 | 自宅で呼吸・いびき・血中酸素などを記録する | 手軽にできる初期検査 | 中程度 | 自宅で可能 |
| PSG検査(終夜睡眠ポリグラフ検査) | 脳波・心電図・呼吸・酸素飽和度、睡眠の質などを総合的に測定 | 正確で詳細な診断が可能 | 高い | 医療機関に一泊入院が原則であるが、自宅でおこなえる検査もある。 |
多くの場合、最初は自宅で簡易検査を行い、必要に応じてPSGで詳しく調べるという流れになります。簡易アプノモニター検査でRDI≒AHI(呼吸障害指数)が40以上、もしくは精密検査(PSG)でAHIが20以上のときにはCPAPという機械での治療が保険適応となります。
睡眠時無呼吸の治療
SASの治療は、原因や重症度に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。以下に代表的な治療法をまとめました。
| 治療法 | 内容 | 対象・特徴 |
|---|---|---|
| CPAP療法(シーパップ) | 寝るときにマスクをつけて、空気を送り気道を広げる | 最も効果が高く、重症・中等症に推奨される |
| マウスピース療法 | 下あごを前に出す器具を使い、気道を確保する | 軽症〜中等症向け。歯科医師との連携が必要 |
| 減量・生活習慣の改善 | 体重を減らす、禁酒、睡眠姿勢の改善など | すべての患者さんに効果あり。根本治療にもつながる |
| 外科手術 | 扁桃や口蓋垂(のどの奥)を切除する手術 | 解剖学的異常がある場合に有効。連携病院に紹介します。 |
| 舌下神経刺激療法 | ペースメーカーのような装置で舌の筋肉を動かし気道を保つ | CPAPが使えない方の新しい選択肢(保険適用あり)連携病院に紹介します。 |
当院ではCPAP療法と、減量・生活習慣の改善に取り組んでいきます。CPAP療法は、継続して使うことで効果が高まるため、使い方のサポートや設定の細かな調整、レポートの判断も行っております。他の治療は連携病院と連携しながら治療に当たります。
睡眠時無呼吸のQ and A
Q. いびきがある=睡眠時無呼吸ですか?
A. いびきがある人すべてがSASというわけではありませんが、SASの多くはいびきが目印になります。放っておかず、一度検査をおすすめします。
Q. 治療は一生続けるのですか?
A. CPAPは長期間の使用が必要ですが、減量に成功したり、他の治療を組み合わせることでCPAPをやめられることもあります。
Q. 子どもでもなるの?
A. はい、子どもでも扁桃腺の肥大や鼻の問題でSASになることがあります。成長や学習に影響するため早めの対応が必要です。
院長より
睡眠時無呼吸症候群は、見逃されやすく、気づかないうちに健康をむしばむ病気で、サイレント・キラーと呼ばれています。昼間の眠気が強い方や、いびきが大きい、呼吸が止まっていると指摘されたことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
当院では、自宅でできる簡易検査から、精密なPSG検査、治療の導入・フォローまで一貫して対応しています(入院でのPSG検査は連携病院で行っていただきます)。CPAPの使い方やマウスピースの相談、生活指導まで、患者さんお一人おひとりに寄り添った診療を行っております。