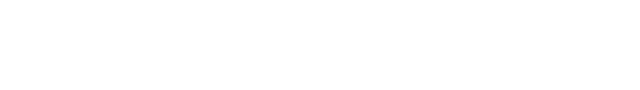肺炎
肺炎とは
肺炎(はいえん)とは、肺にウイルスや細菌などの病原体が入り込んで炎症を起こす病気です。肺に炎症が起きることで、高熱・せき・たん・息苦しさといった症状が現れます。
特に高齢者や赤ちゃん、小さなお子さん、持病のある方では、肺炎が重くなることもあります。風邪と似た症状から始まることが多いのですが、「ただの風邪」と思って放置してしまうと、悪化して入院が必要になることもあります。肺炎は日本人の死因の第5位になっています。(2022年度)
肺炎の原因
肺炎の主な原因は、細菌やウイルスなどです。ご高齢の方や喘息やCOPD、糖尿病など基礎疾患がある方は重症化し、命に関わる病気になりえます。それぞれの原因によって症状や治療方法が少しずつ異なります。
主な原因と特徴
| 原因の種類 | 説明 |
|---|---|
| 細菌性肺炎 | 高熱やたんを伴うせきが出やすく、急に症状が強くなりやすいです。 原因菌は肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌などが多いですが、年齢や基礎疾患により、かかりやすい菌も異なってきます。 |
| ウイルス性肺炎 | インフルエンザウイルス、ライノウイルス、ヒトメタニューモウイルス、コロナウイルスなどが原因として多いです。比較的軽いこともありますが、悪化することもあります。細菌性肺炎との合併も多いです。 |
| マイコプラズマ肺炎 | 非定型肺炎(βラクタム系抗生剤が無効)の一種で、学校などで流行することもあり、比較的若い人に多く見られます。乾いたせきが特徴です。 |
| レジオネラ肺炎 | 非定型肺炎の一種で温泉や24時間循環型風呂、銭湯など水からの感染が多く、重症化することがあります。 |
| 誤嚥性肺炎 | 食べ物や唾液(口腔内の細菌)が気管に入ってしまうことで起きる肺炎です。高齢者や嚥下機能に問題がある方に多く見られます。 |
肺炎の検査
問診(高熱が5日以上続く、脈拍が早い、呼吸が早い、咳がひどい、たんが濃く黄色いなど)や診察(聴診で異常音が聞こえる、酸素飽和度が低下している等)で肺炎を疑うとき、以下のような検査を行います。
| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| 胸部レントゲン | 肺に白い影がないか、炎症が起きていないかを確認します。 |
| 血液検査 | 白血球や炎症反応(CRP)などから、体内の炎症の程度を調べます。 |
| 酸素飽和度測定 | 指にクリップのような器具をつけ、血液中に酸素がどれだけ行きわたっているかを調べます。通常はSpO2 98-97%ですが肺炎の場合低下することがあります。 |
| 原因菌、ウイルスの検査 | その場で原因を特定する方法には、ウイルスに関しては鼻の奥や喉の奥に綿棒を入れて病原体を検出します。マイコプラズマは綿棒で奥や喉をぬぐって検査をします。肺炎球菌とレジオネラ菌は尿検査でその場で結果の確認が可能です。 |
| 痰(たん)の検査 | 出た痰を調べて、どんな菌が原因かを特定します。培養検査(菌を増やす)のため、最終的に数日を要します。 |
| CT検査 | レントゲンではわかりにくい場合に詳しい画像検査を追加します。必要に応じて即日紹介し施行します。 |
検査はどれもそれほど負担がなく、安全に行うことができます。特に早期発見早期対応が大切なので、症状が出たら早めに受診しましょう。
肺炎の治療
抗生物質
肺炎の治療は、原因となる病原体に応じて決まります。細菌性肺炎の場合には主にペニシリン系やセフェム系といった抗生剤を内服や点滴で投与します。非定型肺炎(マイコプラズマ、レジオネラ、クラミジア)にはマクロライド系、ニューキノロン系の内服抗生剤を処方します。年齢や体重、腎機能によって薬剤の投与量、間隔を調整します。重症の場合には関連病院に紹介し、入院での治療を検討します。
細菌性の肺炎には、抗生物質(こうせいぶっしつ)を使います。これは菌をやっつける薬で、飲み薬や点滴の形で処方されます。
解熱剤・咳止め、たん切り(去痰剤)などの対症療法
熱やせきがつらいときには、症状を和らげる薬を一緒に使うこともあります。
入院治療の検討
- 重症の場合(年齢(男性70歳以上、女性75歳以上)、腎障害や脱水、意識障害、酸素飽和度低下(SpO2 90以下)、血圧低下(収縮期血圧90mmHg以下)などで判断します)
- 小児や高齢者や免疫抑制状態、持病のある方
- 自宅での服薬が難しい方
こういった場合には、点滴や酸素投与を行うために入院が必要になることもあります。関連病院に紹介させていただきます。
肺炎についてのよくある質問(Q and A)
Q. 肺炎と風邪はどう違うの?
A. 風邪はのどや鼻(上気道)に起こる軽い感染症ですが、肺炎は肺実質(下気道)に炎症が起きる病気です。高熱や呼吸困難など、症状が重くなる傾向があります。対処療法では改善しないことが多く、治療が必要になります。
Q. 肺炎はうつるの?
A. 肺炎の原因となる細菌やウイルスは人にうつることがありますが、肺炎そのものがうつるわけではありません。ただし、うつった人が体力が落ちていたりすると、肺炎に進むこともあります。マイコプラズマは移りやすい菌として知られています。
Q. ワクチンで予防できるの?
A. 小児に関しては予防接種スケジュールにのっとり、適切に予防接種を行うことが大切です。高齢者や基礎疾患のある方には、「肺炎球菌ワクチン」が有効です。また、インフルエンザ予防や大人のRSウイルスワクチンも肺炎のリスクを下げるために大切です。公費適応されるワクチンもあり、ぜひ当院に相談してください。
院長より
肺炎は、珍しい病気ではなく、放置していても治らず、胸膜炎や膿胸(のうきょう)に進行することがあります。そのため適切な時期に治療を始めることがとても大切な病気です。とくにご高齢の方、基礎疾患(糖尿病・心臓病など)がある方、日頃からせきやたんが続いている方は、肺炎にかかりやすい傾向があります。
「いつもの風邪だろう」と思っても、いつもと違う息苦しさや、発熱が続き、濃い淡が絡んだ咳が治まらないなどの症状があれば、早めに受診してください。